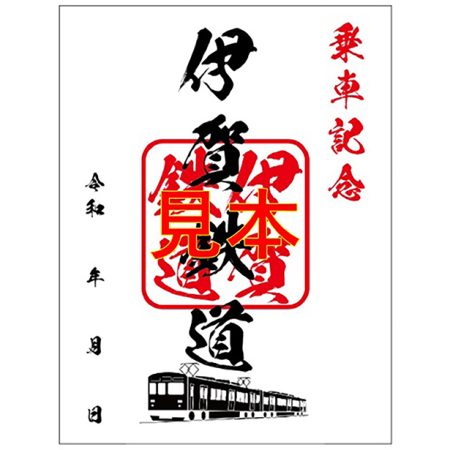Topics
トピックス
神が息づき仏が導く 穐月コレクション
初夏の企画展「神が息づき仏が導く・穐月明と仏教美術の世界」が5月17日から、伊賀市ミュージアム青山讃頌舎(うたのいえ・別府)で始まった。故穐月明さんの、神仏習合の時代の仏教美術や民間信仰についてのコレクションと、作品を合わせて鑑賞する展覧会となっている。
会場に入ると「密教法具と唐時代の金銅仏」と明さんの十一面観音像「大慈大悲」で迎えられ、交互に見ていく内に明さんの松尾寺をモデルにした「雪の寺」。続いて大正新修大蔵経がある。膨大な教・律・論のコレクションに、仏教の全てを知りたかった明さんの強い思いを感じた。
初公開となる「若宮八幡神像」は昨年3月伊賀市の文化財指定を受けた。明さんが所蔵していたが遺族が伊賀市に寄贈したもので、14世紀の名品と言われる。描かれている貴公子は、衣服や容貌から八幡神(応神天皇)の若宮であることから後の仁徳天皇と言われている。絵の右上に「和光同塵 結縁之始 八相成道 以為其終」(わこうどうじん けちえんのはじめ はっそうじょうどう もってなすそのおわり)との墨書があり、仏が親しみやすい神の姿になって衆生に縁を結ぶ本地垂迹説(神仏習合説)の言葉であると、穐月さんの長男で当ミュージアム学芸員の穐月大介さんが解説してくれた。明さんは、あるがままの自然を敬い山河に祈り、仏に救いを求める神仏習合の世界観に親しみを感じていた、と大介さんは話してくれた。
当ミュージアムは大村神社の南側に隣接し、神仏習合の時代には「禅定寺」があったが廃寺となった。その当時本尊だった十一面観音や大般若経百巻は、廃仏毀釈を逃れて伊賀市寺脇の宝厳寺が預かった。十一面観音はパネル展示、大般若経は実物展示されている。元禅定寺にあった虫食い鐘と言われる伊賀市文化財の梵鐘についても大介さんが整理し、今回パネル展示されている。
「日本の神、仏教から来たインドの神、道教的な神、そして仏教、それらが混ざった多様な信仰世界を感じて頂ければ」と大介さんは来館を呼びかけている。
展示は、明さんが描いた作品21点、明さんが集めた古美術品35点、文化財等のパネルが16点合わせて72点。ギャラリートーク「神と仏と山と川と」が6月2日午後1時半から予定されており、講師は大介さん。
当企画展は6月17日まで、火曜日休館。入場料一般300円。お問い合わせ先は伊賀市文化都市協会(0595・52・1109)または、伊賀市ミュージアム青山讃頌舎(0595・52・2100)まで。